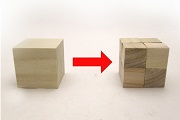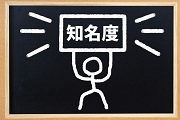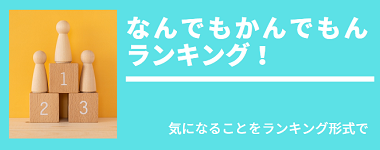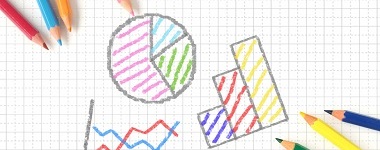最寄品と買回り品|マーケティング用語

消費財には、最寄品・買い回り品・専門品などの分類があります。ここでは、最寄品と買い回り品の違いについて述べます。
最寄品(もよりひん)とは、日常的に使用する製品のうち、自宅や職場などの最寄りの店舗(コンビニやスーパーなど)で購入する商品のことです。最寄品の特徴は、購入頻度が高く、単価が安めであることです。単価が安めで店舗による販売価格に大きな差がないため、わざわざ遠くのお店まで行かなくても、近くのお店で買っておこうという消費者の心理が働きます。企業の側から見ると、如何に消費者の最寄店に商品を陳列できるかが成功の鍵となります。
一方、買回り品(かいまわりひん)は、ある商品を購入するために、いくつかの店舗を回って比較検討するような商品です。洋服や家電製品など、単価が高めで、購入頻度が低めの商品であることが特徴です。昔であれば、実際に複数の店舗を訪問して商品を選定するしかありませんでしたが、現代ではネット(ネットショップや比較サイト)を活用することも含めて、購入までに比較検討を行うものが買回り品です。買回り品の場合には、ネットや店舗などでの他社製品との違い(差別化)の説明において、消費者の心を掴むことが成功の鍵となります。
ちなみに、最寄品には、トイレットペーパーやティッシュペーパーなどをはじめ、日常的に使用する多くの製品が該当しますが、個人の拘りが多様化する現代では、ひとくくりに最寄品と買回り品を区別できないところもあります。