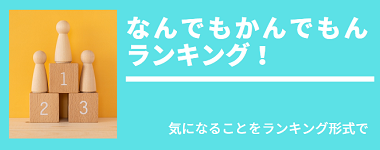プロスペクト理論と損失回避性|経済行動の心理学

プロスペクト理論とは、行動経済学の基礎になる理論であり、人間は与えられた情報から、期待値(事象が発生する確率)に比例してものごとを判断するのではなく、状況や条件によって、その期待値を歪めて判断してしまうというものです。
そもそも、プロスペクト(prospect)という英単語は、「見込み、展望、期待」という意味です。「この先、どうなっていくのだろうか?」という見通しのことです。
例えば、「この先の景気は、どうなるのだろうか?」 という問いに対して、経済評論家は「良くなるだろう/このまましばらくは横ばいだろう/今よりも悪くなるだろう」という見通しを立てるわけですが、この見通しが プロスペクト(prospect)です。
よく、プロスペクト理論で説明に用いられるのは、宝くじです。宝くじに当選して、数億円を手に入れる確率は限りなくゼロに近いはずです。100万円でも、同様です。それでも、人は宝くじを購入します。それは、「当たるかもしれない」と思うからです。
購入する本人も、心のどこかでは、「ハズれるに決まっている。お金の無駄遣いだ。」と思っています。だからこそ、「タバコやお酒をやめて浮いたお金で買うから良いんだ」とか、「買わないことには当たらない」などと、自分に言い聞かせるわけです。
それでも、やはり、限りなくゼロに近い当選確率の宝くじを、自分ならば かなりの確率で当選すると信じて(歪んで認識して)いるから、宝くじを買うわけです。
このように、プロスペクト理論では、事象の確率を歪めて認知する(バイアスがかかる)ことによる人の行動を説明しています。
そして、プロスペクト理論では、「人は損失を避けようとする習性がある」と考えられています。この損失を避けようとする人間の思考の習性を、「損失回避性」と呼びます。
人は目の前に「利益」(例えば10万円を得る)があると、利益(10万円)が手に入らないというリスクを回避しようとします。逆に、損失(10万円を失う)に向き合う場面では、損失(10万円を失う)を回避しようとします。
この説明には、株取引が事例としてよく挙がります。
例えば、株取引をしていて、保有する株の価格が購入時よりも100万円値上げりしたとします。株価は、明日、値下がりするかもしれません。ひょっとして、大暴落するかもしれません。それは、誰にもわかりません。だから、不安になりますし、折角、値上げりした100万円を失いたくないと考えます。元々は、働かずに得た100万円です。それでも、目の前にある100万円を失いたくないので、利益確定のために保有株を売りに出すわけです。
もちろん、明日以降も株価は上昇するかもしれません・・・。
さて、逆に、保有株式が100万円、値下がりしたとします。
対象となる企業の置かれた状況を考えれば、その企業の業績が復活する可能性は低いし、株価が元に戻る可能性も低い。もし、そのような状況に遭遇した場合、株取引の経験が豊富な人であれば、「損切り」を決断します。要は、あきらめて株を売ってしまうのです。
しかし、経験が浅い場合には、深追いをしてしまいます。株価の下落傾向が続く保有株を、買い増してしまうのです。ナンピン買いと呼ばれるものです。
冷静に考えれば、この先も株価が下落する可能性の高い株なんか早く売ってしまって、他の値上がりしそうな株を購入するほうが合理的なはずです。
しかし、「損失を回避したい」という心理が働いているために、危険なナンピン買いを選択してしまうのです。
ところで、世の中には、人間の「損失回避性」を突いた販売促進/キャンペーンが溢れています。
・今だけお得!
・このチャンスをお見逃しなく!
・期間限定!
・先着100名さま!
そんなキャッチコピーが、ネットにも店舗にも溢れ返っています。
それは、「このチャンスを逃したくない。損をしたくない。」という人間の心理に働きかけているのです。
宝くじに話を戻します。
宝くじを買った人は、もし、7億円が当たったら、あんなことをしたい!こんなことをしたい!と夢を見ることでしょう。それを考えるだけでも楽しいものです。しかし、宝くじを買わなくても、妄想にふけることはできます。
では、どうして、人は宝くじを買うのでしょうか?
それは、「もし、ここで宝くじを買わなければ、7億円を手に入れることができない」という機会損失を回避しようとして、宝くじを買っているだけなのかもしれません。