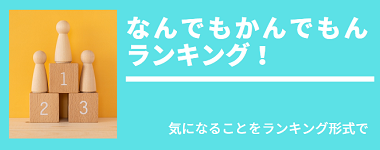おとり効果|経済行動の心理学

おとり効果とは、2つの選択肢でどちらを選ぶか迷っている消費者が、第3の選択肢(捨て案)を提示されることによって、当初の2つの選択肢の一方に誘導される現象のことを指します。
特に、「高機能で高価格な商品」と、「低機能で低価格な商品」を比較検討する際に、それらの商品の機能と価格の関係が妥当であるのかを消費者が判断できない場合には、より効果を発揮します。そして、「高機能で高価格な商品」を選択してもらうためには、欠かせないものです。
実際に、例を挙げて説明します。
あなたが、テレビ番組を録画するための「ハードディスクレコーダー」の購入を検討しているとします。
家電量販店の店頭、あるいは、ネットショップの画面を眺める状況を想像してみてください。
そして、店頭に、あるいは、スマホの画面に、次のような「レコーダーA」と「レコーダーB」の比較表が掲載されているとします。
| レコーダーA | レコーダーB | |
|---|---|---|
| 録 画 時 間 | 100時間 | 200時間 |
| 同時録画できるチャンネル数 | 2 チャンネル | 3 チャンネル |
| 価 格 | 3 万円 | 4 万円 |
どちらかに決めるとしたら、どちらにするでしょうか?
多くの人は、「安いほうで良いかな。そんなに録画容量が大きくなくても良いんじゃないかな。」と思うのではないでしょうか。 もし、録画容量が足りなくなれば、録画した番組を小まめに消去すれば良いわけですし。
ここで、一旦、リセットです。
家電量販店の店頭、あるいは、ネットショップの画面を眺めたときに、最初に、次のような「レコーダーA」「レコーダーB」「レコーダーC」の比較表が掲載されているとします。
| レコーダーA | レコーダーB | レコーダーC | |
|---|---|---|---|
| 録 画 時 間 | 100時間 | 200時間 | 150時間 |
| 同時録画できるチャンネル数 | 2 チャンネル | 3 チャンネル | 2 チャンネル |
| 価 格 | 3 万円 | 4 万円 | 6 万円 |
商品が3つ並んでいるので、先ほどよりも比較に時間がかかるはずです。
最初にどこに視点を落として、何と何とを比較するのかは、人によって異なるでしょう。
しかし、ある程度の時間が経てば、誰もが気づくはずです。「レコーダーC」の商品力のなさに。
そして、自信たっぷりに思うはずです。「Cはないな」と。なぜならば、「レコーダーC」は「レコーダーB」に比べて、機能が劣る上に、価格が高いわけですから。
そして、こんなふうに思うかもしれません。
「こんな商品を売ってるなんて、なんて可哀そうなメーカーなんだろう。消費者のニーズや、競合商品のことを何も知らないんだな。」
「こんなの誰が買うんだ?」
あなたは、「レコーダーC」に対して、怒りに似た感情すら抱くかもしれません。
それくらいに、「レコーダーC」は駄目な商品であることが、あなたの心に刻まれるわけです。
その後、「(駄目な)レコーダーC」と「レコーダーA」を比較してみます。
すると、「レコーダーA」の値段は安いけれど、録画時間が「レコーダーC」よりも短いことが気になります。あの、とんでもなく駄目な「レコーダーC」よりも、「レコーダーA」には劣っている機能があるのです。
そこで、あなたは、考えます。
「レコーダーB」は、「レコーダーA」より少し価格は高いけれど、「録画時間」が長いんだから価格が高いのは当然なんだろうな。 そして、機能的に他の商品よりも優れていて、価格もそこそこな「レコーダーB」こそが、自分が買うべき商品なんだ、と。
このように、「レコーダーC」が登場したことによって、あなたが「レコーダーB」を選択する確率が高まるわけです。
これが、『おとり効果』というものです。