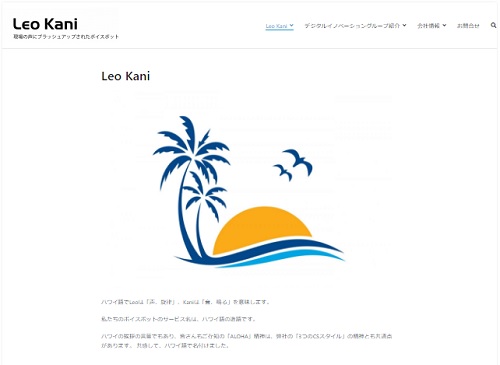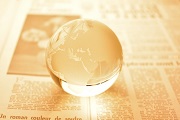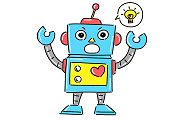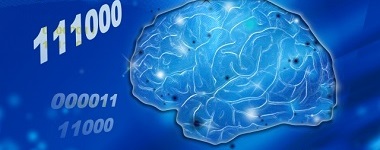あふれ呼と深夜早朝コールセンターにボイスボットという選択肢

● AIの1つの分野である自然言語処理
人工知能(AI)が人間の知能を上回るときをシンギュラリティと呼びます。今世紀のどこかでそのシンギュラリティが実現して、人間の代わりに人工知能が仕事をしてくれる。人間は働かなくても良くなる。そんな未来を想像する人達がいます。
でも、そんな未来が本当にやってくるのでしょうか?
チェスや囲碁で人間のチャンピオンを相手にAIが勝利するようになりました。それを見て、いよいよ、AIが人間の知能を追い越したと大騒ぎする人達がいます。
しかし、人工知能には いろんな分野があります。
チェスや囲碁で戦うAIは「画像認識」や「パターン認識」と呼ばれる技術分野がベースであって、それが飛躍的に進歩した背景にはディープラーニングという推論方式の出現があります。ただし、このディープラーニングは、全くゼロから誕生したものではありません。何十年も前から存在するニューラルネットワーク(人間の神経細胞を参考にした推論モデル)を発展・深化させたものです。ディープラーニングはニューラルネットワークの中間層を多段化したものなので、(いわゆるゼロイチの)クリエイティブなアイデアではないという言い方もできます。
このディープラーニングの活躍には、コンピューターの計算能力の向上が背景にあります。30年前は、単なるニューラルネットワークでさえコンピューターの計算能力不足に悩まされていたものです。その計算能力を補うために、ニューラルネットワークを並列処理させる研究もされていました。
しかし、時は流れて、現代では最高速のスーパーコンピューターでなくても、ディープラーニングを実装できるほどに、コンピューターの処理能力が向上しました。その結果、「画像認識」や「パターン認識」の分野ではAIが飛躍的な進化を遂げました。そして、人間の医師が見落とすような病気の兆候を、AIがレントゲンやCTの映像から見つけ出してくれる。そんな医療分野などへの応用が期待されています。
AIの研究分野には、その他に「自然言語処理」という分野があります。
自然言語とは、人間が使っている言語(日本語や英語など)のことです。コンピューターサイエンスの世界で「言語」と言えば「プログラミング言語」(BasicやC言語など)のことを指すことが多いため、日本語や英語のことをわざわざ「自然言語」と呼んでいます。
その自然言語をコンピューターで取り扱うのが「自然言語処理」です。
人間のように喋るロボット、電話の向こうで応答してくれるボイスボット、話しかけると好みの映画や音楽を探し出してくれるスマートスピーカー。それらを支える技術が「自然言語処理」です。
昔に比べれば、自動翻訳もかなり精度が高くなりました。ネットでGoogle翻訳を試してみれば、かなりの精度で翻訳してくれることに感心します。それでも、それなりの頻度で「さっぱりわからない」と感じる訳文を目にすることもあります。
その自然言語処理が、「テキスト」から「話し言葉」になれば、一層、処理は難しくなります。
そもそも、英語に比べて日本語には「あいまいさ」が多く含まれます。その最たるものは、主語がなくても人間(日本人)には意味が通じるというところです。目の前の人に対して、「あなたは」という言葉を省略しても意味は通じますし、「あれ」や「これ」で話を進めることも出来ます。
しかし、コンピューターにとって、「あいまいさ」は最大の障壁です。どんなに優れた分析方法を用いても、どれだけ高速なコンピューターを使用しても、「あいまいさ」は根本的に解決できない問題です。
● コールセンターのオペレーターは、本当に消滅する職業なのか?
少し前に、「AIによって消滅する職業」が話題になりました。コールセンターのオペレーターもその一つとして挙げられました。恐らく、英語圏のインテリ層の発想は、次のようなものではないでしょうか。
コールセンター業務は付加価値の低いものであって、企業はコアな部分に経営資源を集中するべきだ。だから、コールセンターを自社で抱えずにインドやフィリピンへアウトソーシングすれば良い。そして、その先は、AIに置き換えてさらにコスト削減を実現するべきだ、と。
しかし、実際にコールセンター運営に関わる人間からすれば、それが絵空事であることがすぐに理解できるはずです。
インバウンドコール(受信業務)のコールセンターには、何かに困っているお客さま、怒りに震えているお客さまなど、いろんな方から電話が架かってきます。人間のオペレーターでも応対するのには、それなりのスキルが必要です。話の内容に加えて、声の大小・高低・抑揚などがより重要になります。もちろん、日本語の敬語もきちんと使いこなさなければなりません。
その上に、日本語の「あいまいさ」の処理が必要になります。思い込みで間違ったことを言い出すお客さまもいるでしょう。大事なキーワードをド忘れてしまって「えっと、なんだっけ、ほら、あれよ、あれ」と言い出すお客さまもいるでしょう。
困って電話をしてきた人は、ボイスボットの対応では結局何の解決にも至らずに、二度と電話をしてこなくなるかもしれません。また、怒りに震えて電話してきた人は、ボイスボットの対応に怒りの感情を爆発させるかもしれません。
また、アウトバウンドでの営業電話は、電話業務の中で最も難しい仕事の1つです。電話先の顧客の興味関心の度合いを測りながら、セールストークを展開する。それをボイスボットで代替することは本当に可能なのでしょうか?
● ボイスボットの現実的な利用シーン
ネット通販やネット予約など、ウェブやスマホアプリで処理できるものが世の中にはたくさんあります。逆に、人間のオペレーターでないと処理しきれない顧客対応もたくさん存在します。
そのような中で、ボイスボットはどのような場面に活路を見出すことができるのでしょうか?
まず、考えられるのは、これまで取りこぼしていた顧客への対応です。
コールセンターの処理能力には限界があります。いくら回線数を増やしたとしても、オペレーターの数を超えるコールには対応できません。そこで、これまで取りこぼしていたコール(あふれ呼)への対応としてボイスボットの活用が考えられます。オペレーターの数を超えたコールについては、ボイスボットが対応する。そんな顧客対応の方法です。
また、これまでは平日にしか対応していなかったコールセンターを土日祝日も稼働させたい。あるいは、深夜早朝帯にも対応したい。そんな場面にもボイスボットは有効かもしれません。いつどれくらい架かってくるかわからないコールのためにコストをかけて人員を配置するのは厳しいでしょう。コアタイムはオペレーターで対応して、それ以外はボイスボットで対応する。そうやって、24時間×365日のコールセンターを実現するという選択肢があります。
まだまだ発展途上のボイスボットですが、このようにこれまで取り組めていなかった領域を補完する位置づけであれば、一度、試してみようかと思われた方もいらっしゃるでしょう。
もし、ボイスボットの活用にご興味をお持ちいただけましたら、当社のデジタルイノベーション専用サイトからお問合せください。