2022.08.22
bpo・アウトソーシングサービスの活用は、日本社会の必然的な流れ。
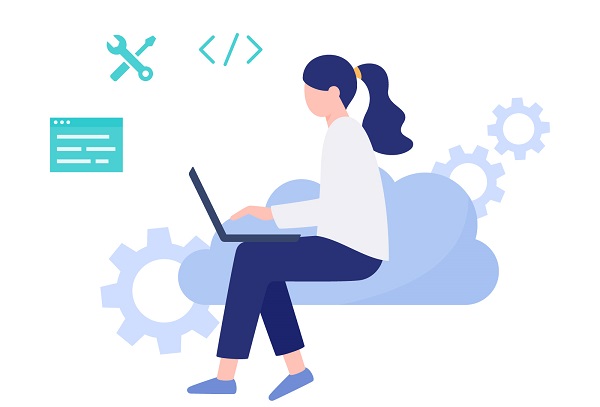
飲食・観光・旅客など、コロナ禍で経営の苦しい業界・企業がたくさん存在します。本当に経営が厳しくなれば、従業員を関連会社に出向させたり、最悪の場合は解雇することになります。
一方で、コロナ禍の影響を受けずに、業績の好調な業界・企業があります。巣ごもり需要に支えられた、ネット動画やゲーム関連、それに通販などの企業が、その代表でしょうか。実は、業績の好調な企業は、人手不足に苦しんでいます。業務を拡張したくても、人手が足りません。人手があれば、いくらでも業績を伸ばすことができるのに。人が欲しいけれど、人がいません。
従来から指摘されているとおり、日本では人材の流動性がありません。雇用される側からすれば、余程の事情がない限り解雇されないというシステムは安心ではあります。しかし、一旦、解雇された人にとっては、働く場所を探すことは大変なことです。だから、そうならないように、あまり余計なことをしないで、細く長く今の待遇を維持しようと萎縮してしまうのかもしれません。
企業の経営者の立場からすれば、一度、雇った従業員(正社員)は、定年退職になるまで雇い続けなければなりません。その定年退職も、今は60歳が一般的ですが、そのうちに65歳や70歳に延長されるかもしれません。
だからと言って、派遣社員に依存してしまうと、事業の継続に支障をきたす可能性もあります。派遣社員は、3年間しか同じ職場では働けないからです。同一労働同一賃金の流れにより、派遣社員や契約社員の待遇改善が期待されますが、経営者側すれば、頭が痛い話です。
また、若い人は、少子化の影響で、売り手市場になっています。知名度の低い企業や、イメージの良くない企業には、若い人は入社してくれません。親たちも、より安定した企業への就職を望むはずです。
そのような日本の社会事情を考えると、特に、間接部門については、直接、社員を雇うよりも、BPOやアウトソーシングサービスを活用しようと考えるのは、自然な流れなのかもしれません。
日本企業の情報システムが、企業内の汎用計算機(ホストコンピューター)から、社内でのクライアントサーバーモデル、あるいは、データーセンターへのホスティングやレンタルサーバーの利用を経て、現在のクラウドサービスの利用へと変化したように、間接部門の人的資源は、直接採用から契約社員や派遣社員の活用を経て、BPOやアウトソーシングサービスに収れんされていくはずです。
水が高い場所から低い場所に流れていくのと同様に、今の日本社会のシステムの下では、それが当然の結果なのかもしれません。